公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(CFC)
子どもの「体験格差」をなくす。
生活困窮家庭の子どもたちを支援するチャンス・フォー・チルドレン
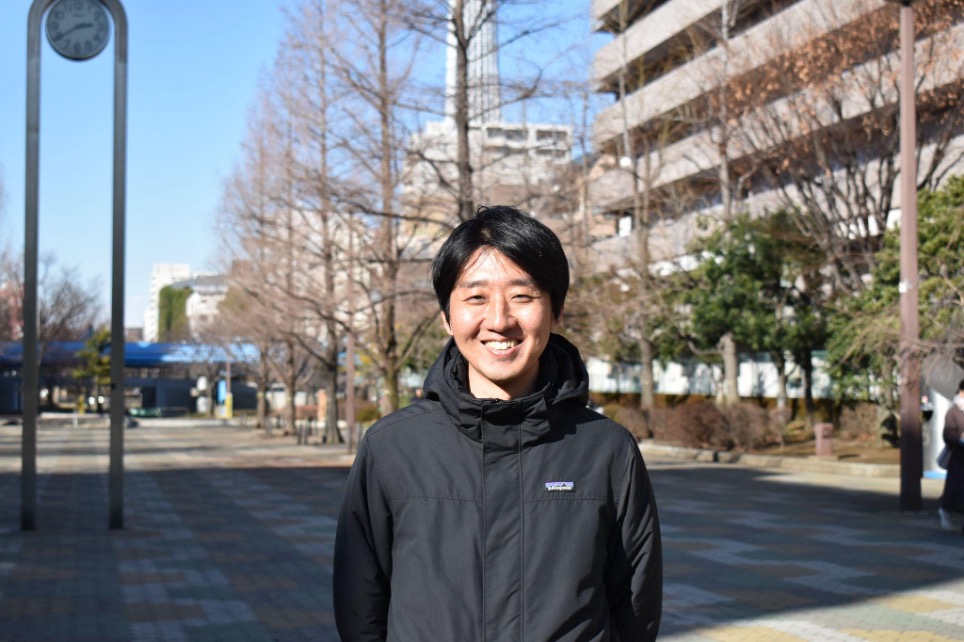
家庭の経済格差による子どもの教育格差を解消する支援活動を通して、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目指している、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(以下、CFC)。近年、学習機会の格差だけでなく、スポーツや芸術・文化といった体験機会の格差も解消するべく新たな事業もスタートさせ、子どもたちの未来の可能性を広げる活動を全国各地で展開しています。 今回は同団体の代表理事である今井悠介さんに、活動経緯や墨田区を起点にどのような展開をされようとしているのか、取り組みへの想いをお聞きしました。
子どもの選択肢を広げる スタディクーポン
2011年設立のCFCは、経済的な困難を抱える子どもたちに、学習塾や習い事、体験活動などで利用できるスタディクーポンを提供しながら、教育格差の解消を目指して活動をしている団体です。「子どもたちの学習やさまざまな体験の格差をなくし、貧困の連鎖を止めていきたいんです」と活動への想いを話してくれたのは、代表の今井さん。
兵庫県神戸市生まれの今井さんは、自身が小学2年生の時に阪神・淡路大震災を経験。その後、大学在学中に学生ボランティア団体「NPO法人ブレーンヒューマニティー」に所属し、子ども向けのキャンプやスタディーツアーの実施、不登校の子どもへの支援活動など、さまざまな体験機会をつくってきました。そんな中、2008年にリーマンショックによって経済情勢が悪化し、「家庭の経済状況によって、学校外の活動に参加できない子どもが増え、体験格差が生まれることに大きな課題を感じた」という今井さん。そこで、学生たちが募金で集めた寄付金を原資に学校外での教育費をサポートする事業を行っていきました。
大学卒業後、学習塾の運営に従事するなどして、学生時代から長く子どもたちの「学び」に携わってきました。そんな中、2011年に東日本大震災が発生。これを契機に本格的に教育格差の問題に取り組むことを決意し、同年、NPO法人ブレーンヒューマニティーから独立する形で、CFCを設立しました。

設立以来、経済的に苦しい環境にある子どもたちを対象に、塾や予備校、習い事などの学校外の教育活動に利用できる「スタディクーポン」を提供してきました。具体的には、子ども1人につき年間数万円~数十万円分といった教育活動の補助をします。文化活動やスポーツ、体験活動などさまざまな選択肢の中から、子どもがやりたいと希望するものを選ぶことができます。また、大学生ボランティアが定期的に電話や面談で学習や進路相談にのる「ブラザー・シスター制度」があり、子どもたちを継続的に見守りながら学びの後押しをします。

2023年度は700名の子どもたちに総額1億6,830万円分のスタディクーポンを提供し、東北エリアでの支援から始まったこの取り組みは、今では関東エリアや関西エリアにまで広がりを見せています。
経済的理由から生まれる「教育格差」
設立から約13年間でのべ6,000人以上の子どもたちに、総額約12.5億円分、さらに全国6つの自治体(2024年3月時点)とも協働し、のべ19万人以上もの子どもたちにスタディクーポンを届けてきたCFC。
それでも、まだまだ支援が届けられていない子どもたちが大勢いるのが現状です。CFCの活動は寄付金によって支えられています。支援をさらに広げ、活動を継続していくためには「理念と事業をやる理由を明確に伝え、共感してもらえる人たちを増やすことが重要だと考えています」と今井さんはいいます。
「私たちは学びの場をつくるのではなく、クーポンの提供、学生ボランティアとして参加、個人での寄付といった、子どもたちの支援に関われる仕組みをつくっています。さまざまな形で参加できることを知ってもらえるようにしていきたいです」

CFCが墨田区に拠点を持つことになったのは、亀戸で活動するNPOがCFCの理念に共感し、事務所の一角を貸してくれることになったのがきっかけなのだそうです。以来、墨田区に住まいも構えながら、地域の中でさまざまな事業者たちとつながりを深めてきたという、今井さん。
「墨田区の人たちは、地域が良くなって欲しいと思う人たちが多いという印象が強いですね。協力したいと積極的に声をかけてくれる方たちが多くて。なにより、いろんな人たちとつながっていく実感を得られます」
そんな地域の魅力も感じながら、CFCの活動を通してより地域の中でのつながりや連携を加速させていきたいと、2022年に墨田区で「ハロカル(ハローカルチャー&ローカル)」という新たな取り組みをスタートさせました。
地域の大人たちと共に、体験を後押し
CFCが2022年に日本初の「体験格差」の大規模な実態調査を行い、調査結果を会見で発表するとマスコミが取り上げ話題を呼びました。全国の小学生や保護者に実施した調査では、年収300万円未満の家庭では約3人に1人の子どもが、1年間で1度もスポーツや音楽、キャンプといった学校外の体験に参加できていないという実態がわかり、「体験格差」は社会問題として世間に知られることとなりました。
「私自身もさまざまな体験によって人生の選択肢が広がっていくことを実感してきました。子どもたちが視野を広げることや、価値観を形成していく上で体験機会は欠かせないことだと思うんです。それを地域で想いを持って活動をする大人たちにも見守ってもらえるような仕組みが必要だと考えていました」

子どもたちに豊かな体験の機会を届けようと始めた、ハロカル。この名前には「ハロー・カルチャー(文化・体験との出会い)」と「ハロー・ローカル(地域との出会い)」の2つの意味が込められています。主に経済的に厳しい家庭の小学生を対象に、支援者の寄付金を原資にして、スポーツや音楽・芸術活動などで利用できる奨学金を提供するというもの。地域にあるNPOなどと連携して奨学金という形で体験機会を届け、子どもたちの成長を地域で支えていこうとする取り組みです。
「教室やクラブを運営する大人たちは、それぞれ想いを持ってその地域で始めた方たち。地域での活動を大切にしてきたからこそ、子どもたちの成長にできることはないかと考えている方も多いんです。教えるということだけでなく子どもたちを見守っていく、つながりをつくっていくといった考えが拡がっていくと体験格差もなくなっていくと信じています」

CFCの本部がある墨田区では、「体験格差をなくす」という想いに共感した60以上の教室やクラブが参画し、審査によって奨学金の提供を受けた約60人の子どもたちが音楽やスポーツ、野外活動などの体験をしています。今後も参画パートナーを増やしていきたいと、今井さんは考えています。
家と学校とは異なる地域の人との関わりが生まれたことで、親子関係が良好になったり、大人との関わりが苦手だった子どもが少しずつ自分の意思を示すようになったりと、子どもや親にも前向きな変化が生まれているそうです。
「子どもたちが『やってみたい』と素直に言えて、できることが当たり前の環境ができたら嬉しい」と話す今井さん。墨田区を皮切りに、岡山県岡山市や宮城県石巻市、沖縄県那覇市など4つのエリアへと事業を展開しています。今後も地域の人たちが主体となって子どもたちをサポートしたり、地域の中でのつながりを深めていきながら、持続可能な仕組みにしていこうとしています。

子どもたちにメッセージ
一人ひとりが「やってみたい」こととつながっていけるように、「やってみたい」を実現するハードルをなくしていくために、私たちはこれからも活動を続けていきます。地域の中にはおもしろい大人がたくさんいます。みなさんの「やってみたい」ことの中から、まちの大人たちとつながってみてください!
