フットマーク株式会社

一人の声をカタチにする。
フットマークが伝える、ものづくりの魅力
1946年創業のフットマーク株式会社は、水泳用品や介護用品で長く愛されるロングセラー商品を次々と生み出してきた墨田区が誇るものづくり企業。心と体の健康に役立つ商品を世に出し続けられた背景にはどのような想いや行動があったのでしょうか。今回は、同社の代表取締役社長・三瓶芳さんと学校教育事業部で新商品のスクール水着の開発を担当した木村元気さんにフットマークのものづくりで大切にしていることや魅力をお聞きしました。
商品づくりの根底にある、お客様第一の姿勢
フットマークは赤ちゃんのおむつカバーを製造する会社として誕生しました。1960年代後半に学校用の水泳帽子の開発・製造・販売に事業転換し、ロングセラー商品となり現在でも全国シェアNo.1を誇ります。

1980年代には新たな分野として介護用品の展開もスタートさせ、当たり前に耳にするようになった「介護」という言葉はフットマークが商標登録をしました。現在は水泳用品や学校用品、アウトドア用品、健康・介護用品の企画・製造・販売へと商品展開を拡大させてきました。時代の流れと共に、世の中のニーズをキャッチして先進的なものづくりを行い、現在は健康をテーマとした商品づくりに注力しています。

「フットマークが大切にしていることは、1/1(いちぶんのいち)の視点。お客様の声に丁寧かつ謙虚に耳を傾けることからものづくりが始まります。データやリサーチに基づく商品開発も大切ですが当社はたった一人の声も大切に、オンリーワンの商品開発を心がけています」と話すのは、同社の代表取締役社長・三瓶芳さんです。

三瓶さんは1980年に同社に入社し、製造・営業・物流といったあらゆる職種を経験しながらものづくりの魅力を実感してきました。自身の開発実績のひとつとして思い出深いのは、かわいらしいアニマルの耳がついたベビー用水泳帽子「アニマル君」だといいます。
「ベビー水着の開発で水泳教室に足を運んだ際に、コーチは幼児のスクール生をあやしながら指導にあたっていました。三瓶さんは、コーチや指導者から『あやすためのものがあったらいいのに……』という声を聞き、ベビー用水泳帽子を開発しました。

「赤ちゃん同士がかぶればお互いに関心を持ってくれるし、あやす手間も省くことができます。この帽子をかぶれば、子どもたちの水慣れにも役立つと思ったんです」と製品の経緯を語ります。1987年の発売以来、36年以上経った今でも販売が続くロングセラー商品となりました。
「最近、この商品で嬉しい出来事があったんですよ。自社主催のイベントに参加した高校生が、『赤ちゃんの時にこの帽子をかぶって水泳をしていました』と声をかけてくれたんです。感慨深かったですね」とにこやかに話す三瓶さん。
2012年の代表就任以降も、ものづくりへの情熱は続いています。
「お役に立てるものをつくりたい、必要とされる会社でありたい、という思いは変わっていません。ものづくりに大切なのは、お客様第一の姿勢です。社員にもものづくりの面白さ、カタチにして世の中に出せる体験をできるだけ多くしてほしいと願っています」

フットマークでは毎年3000品番もの商品をつくっており、そのうち1000品番は新しく入れ替えを行っているそうです。イベントやアンケートを通して得られるお客様の声や情報を吸い上げ、営業と開発担当が4、5人程度の少人数のチームとなって日々の業務を行っています。
「商品化に至るまでは大変なこともありますが、カタチにするためには担当者自身の想いの強さがとても重要だと考えています。担当者一人ひとりがお客様の困りごとをしっかり認識し、理解するように努めてほしいと伝えています」 ものづくりの一歩やヒントは、自分の身近なところにある、と三瓶さんは考えています。
「着用する人にとっていいものとは?」を追求した水着開発
フットマークでは、1978年に自社で初めてのスクール水着を販売開始以来、水着に名前を記入する「ネームライン水着」、縦横に伸縮性のある生地を採用した「ツーウェイ水着」、スイミングクラブで好評だったものを学校水泳にも取り入れた「アクアライン水着」、フィットネスブームとなった2000年には「オールインワン水着」、高機能スクール水着など、時代の変化と共に学校現場のニーズを捉え、次々と先進的な水着を開発してきました。 そして2022年、ジェンダー問題の解決の一助となる「男女共用セパレーツ水着」の販売を新たにスタート。開発担当者として奔走した学校教育事業部の木村元気さんに開発経緯やこだわりの点を聞いてみました。

入社20年目の木村さんは、飲食業界、物流事業を経てフットマークの事業拡大のタイミングで誘いの声がかかり、中途入社をしました。「前職の物流会社でフットマークの商品を扱っていたのですが、社員の人たちが生き生きしている雰囲気や人柄に魅力を感じていたんです」と入社理由を話します。
そんな木村さんが「男女共用セパレーツ水着」の開発に挑むきっかけは、5年前の1本の問い合わせ電話からでした。「お取引先が学校から『ジェンダー問題で悩む生徒が着られる水着はありますか』と尋ねられたと連絡がありました。当時、男女共用の水着という発想がなく、その時はラッシュガードを着て、下はサーフパンツを重ねて着ることを提案しました」と振り返ります。しかし、その問い合わせ以降、同様の相談を受ける回数が増え、「自分が思っている以上に困っている生徒がいるんじゃないかと思うようになっていった」という木村さん。社内で商品化の提案をしましたが、前例のない商品であったことから学校の動向を見ながら、開発時期を見極めていたそうです。
そのうち、学校制服でジェンダーレス化の動きが出てくるようになり、学校現場でも関心が高まってきた中で開発に着手。こうして、生徒たちの「肌を見せたくない」「体型を隠したい」「日焼けしたくない」といったさまざまな悩みを解決する水着として誕生したのが、男女共用セパレーツ水着です。

体型に関係なく着用できるゆったりした設計で、サーフパンツにすることでヒップラインが気になる生徒にも着やすいシルエット、さらにジップ仕様になっているので着脱も容易です。


上着のめくれ防止にループを縫いつけたり、水着が膨らむのを防ぐための空気の抜け穴をつくったり、撥水加工を施したりと、身体的、機能的な不安箇所や課題を一つひとつ丁寧に検証しながら作り上げました。
木村さんは水着の商品名にもこだわったと話します。
「学校関係者などビジネスの観点でいえば『ジェンダーレス水着』としたほうが伝わる言葉かもしれません。しかし、社内では実際に水着を着用する生徒にとっては商品名を見て抵抗感が生まれたり、手に取りづらかったりしないだろうかという議論があり、誰もが着られるということを伝える『共用』という言葉を採用したんです」
使う人に寄り添う姿勢は、商品づくりだけにとどまらずネーミングにも反映されています。ありそうでなかった新たな水着の提案は、公立中学校を中心に多くの学校から注目を集め、2024年度以降はすでに300校以上の導入が決定しているそうです。
「ジェンダーレスの水着、というところから開発がスタートしましたが、結果として水泳の授業の参加率にもつながるという学校の声も聞きました。学校の水泳授業は水中で自分の命を守るために必要な学びの機会だと思います。参加率の低下の要因の中に水着もあるとしたら、水着のアップデートをすることを通して、その課題解決につなげられたら嬉しいです」と木村さん。
「目の前のお客様を助ける、ということに重きを置いている会社だと思っています。私たちが学校用品を企画・開発したことで、学生さんたちが喜んでくれたり、役に立っていたりという声を聞くと、次の開発のモチベーションになります」とフットマークでのやりがいを実感しながら、よりよい製品をつくろうとしています。
ものづくりの楽しさとやりがいを未来につなぐ
お客様の声一つひとつに商品づくりのヒントがあると考えている、フットマーク。学校用品など子どもや学生向け商品も多数取り扱うので、子どもたちから直接聞ける意見やアイデアはとても貴重です。そこで、学生の職場体験受け入れや水泳教室、学生との商品開発、国内外の水泳振興の支援などを積極的に行っています。
例えば、ものづくり体験の機会として行っているワークショップ。2023年夏には本社に併設する小さな博物館「フットマークギャラリー」で、夏休み自由研究お助け企画として「世界で1つだけの水泳帽をつくろう」というイベントを実施しました。

看板商品である水泳帽子の歴史を学んだうえで、子どもたちが生地の裁断、帽子の配色を決め、最後に社員が縫製をして帽子を実際に作ってみる、という企画です。作る楽しさを知り、プロの技術を直に見られる貴重な機会に、子どもたちが熱心に取り組む光景に喜びを感じたそうです。
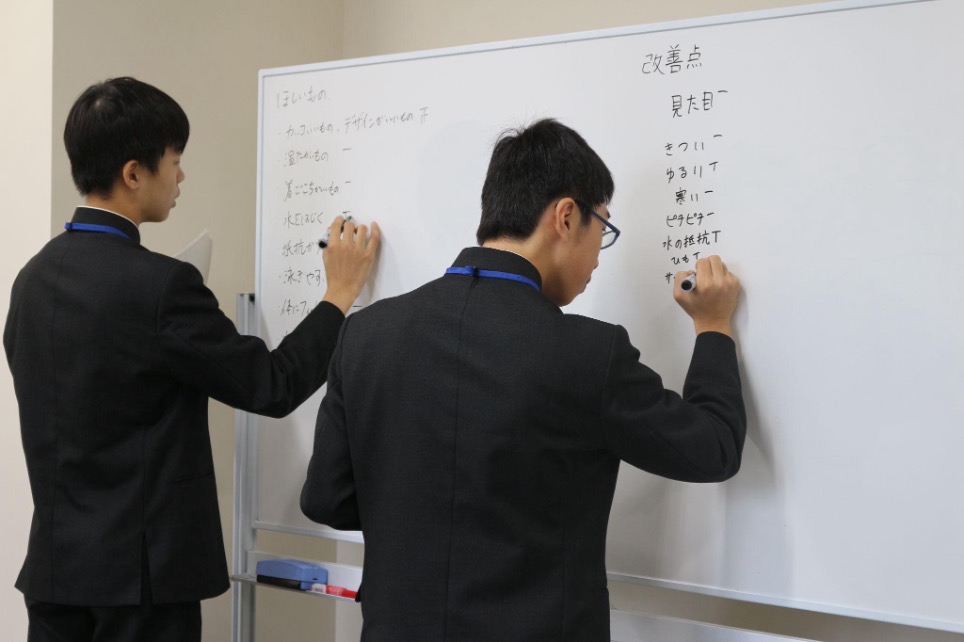
過去に実施した中学生から大学生までを対象にした「ものづくりプロジェクト」では、学生たちの視点でスクール水着やスクールカバンの開発を通して、学生たちの豊かな発想や好奇心旺盛な様子を見た三瓶さん。「お客様のほうが商品のことをよく知っているということを改めて実感し、求めているものを直接聞く大切さ、そしてメーカーはカタチにするお手伝いができる体制をつくることがものづくりを未来につなげていくことだと感じた」と話します。
どんなに時代や産業の移り変わりがあっても、人を想い、一人ひとりの笑顔を創っていこうという想いを込めて、フットマークは「健康快互(けんこうかいご)」という言葉を掲げ、商品開発に努めています。

「ステークホルダーの中で私たちフットマークは活かされています。お客様も社員も関係者もそれぞれ心地よくいられる関係を大事にしながら、これからもいろんなことに取り組んでいきたいですね。お客様に寄り添い、お役立ちできることを提案し続け、今後は健康や介護の一翼を担える会社になっていきたいです」と力強く想いを語る三瓶さん。「あったらいいのに……」という声がある限り、フットマークのものづくりに終わりはありません。
「困っている人の力になりたい」という強い想いと行動力で、これからもさまざまな課題に果敢に挑戦し、フットマークのものづくりを未来に紡いでいこうとしています。

